「棺に10円玉を入れるのはなぜ?」と疑問に思った方は多いのではないでしょうか
葬儀や供養の場で耳にするこの習慣には、昔からの風習や宗教的な意味合いが込められています
しかし近年、札幌市が「棺に10円玉を入れること」について注意を呼びかけたことで、さらに関心が高まっています

結論から言えば、10円玉を入れる行為には一見すると納得できる理由がありますが、実際には思わぬリスクも潜んでいます
本記事では、棺に10円玉を入れる風習の由来、札幌市が警告を出した背景、そして現代における正しい供養のあり方について詳しく解説していきます
棺に10円玉を入れる風習の由来
三途の川の渡し賃や六文銭といった考えが古くから日本にあり、あの世へ行く際の「渡し賃」や安全祈願として副葬品を納める習慣が生まれました
時代や地域によって形は異なりますが、火葬が主流になった現代でも地域的に銅銭や10円玉を棺に入れる風習が残っていることが知られています
文化的・歴史的な背景としては、古代からの副葬の考え方がそのまま地域習慣に連なっている点が大きいです
10円玉と三途の川の関係
「三途の川の渡し賃」と結びつけて、棺に金銭や模した紙銭を入れる風習は各地に見られます
北海道など一部地域では、六文銭の代わりに10円玉を用いる慣習が受け継がれてきたため、「お守り」や「渡し賃」として入れる人がいるのです
伝承と家族の思いが混ざり合った行為であることが多く、単なる迷信ではなく故人への思いの表現でもあります
日本各地に残る棺と貨幣の風習
一方で、日本各地の習俗は多様で、紙銭を使う地域、金属を直接入れないで紙に銭を書いて納める地域などがあり、火葬方式や地域のしきたりに合わせたやり方が定着しています
現代の葬送習慣は安全面や環境面の配慮から変化しており、伝統と現実の折り合いをつける必要が出ています
海外における「棺と貨幣」の類似文化
アジアを中心に、あの世で使うための貨幣や紙銭を副葬する文化は古くからあり、中国・韓国・ベトナムなどでも紙銭(冥銭)を焚く習慣が見られます
地域差はあるものの、「あの世で困らないように」という発想は世界的な人間の感情と結びついています
棺に10円玉を入れるのはなぜ危険なのか
札幌市が「棺に10円玉を入れないでほしい」と周知を強めた背景には、火葬作業や火葬炉の運用に与える実害が明確にあります
硬貨が高温で溶けたり付着したりすることで炉の損傷や耐用年数の低下を招き、修理や交換といったコストや稼働停止による市民への影響が生じるためです
札幌市は増加する火葬件数と併せ、火葬場設備を守る観点から呼びかけています
札幌市が警告した具体的な理由
札幌市の火葬場では、棺に入れた10円玉が溶けて炉内の台座や内部に付着し、剥がれにくくなる事例が報告されています
こうした付着は炉の効率を下げるだけでなく、メンテナンスの頻度を上げる原因になります
市はイラスト入りのチラシを作成し、住民へ注意を呼びかけるなど周知を強化しています

火葬時に発生するトラブルとは
金属類が炉内で高温にさらされると、炉の内部構造を損なうだけでなく、遺骨の一部が変色したり、溶けた金属が骨に付着したりして遺族の意向にそぐわない結果を招くことがあります
またプラスチックや合成繊維を含む副葬品が燃えると、ダイオキシン類や有害ガスが発生するリスクが高まり、環境負荷や作業者の安全にも影響します
こうした理由から多くの自治体や火葬場は副葬品の制限を設けています
金属の影響による炉の損傷
硬貨や金属製品は燃えないため、溶融して炉内に付着したり、局所的な熱変化を引き起こして金属疲労や耐火材の損傷につながることがあります
火葬炉は高温管理が重要な設備であり、想定外の異物は設備故障の原因になり得ます
自治体はこれを避けるため「金属類は入れないでほしい」と呼びかけています
ダイオキシンなど有害物質の発生リスク
プラスチック類や化学繊維の焼却はダイオキシンや塩化水素などの有害物質を生む可能性が指摘されており、その発生は環境問題としても重大です
火葬場側は排ガス処理を行っている場合が多いものの、完全に無害化することは難しく、副葬品の持ち込みを制限する理由の一つになっています
棺に入れてはいけないもの一覧
多くの火葬場や自治体が示す基準では、燃やすと有害物質が出るもの、爆発や発火の恐れがあるもの、炉を損なう金属類は避けるべきとされています
例えばスプレー缶や乾電池、ペースメーカーなどは爆発の危険があるため事前に取り外すか係員に相談する必要があります
地域によって多少の運用差はあるため、事前に葬儀社や火葬場へ確認することが重要です
金属類(硬貨・指輪・眼鏡など)
金属は高温で溶けたり付着したりして炉の損傷や遺骨の変色を招く可能性があるため、多くの斎場で持ち込みを禁じています
指輪など貴金属については事前に取り外して遺族に保管するのが一般的です
炉を守り、遺族のためにも金属類は原則として棺に入れない方が安全です
爆発や発火の恐れがあるもの(缶・ライターなど)
缶詰やライター、乾電池などは火葬時に内部圧力で破裂することがあり、作業者の安全や炉の安全運用に影響します
こうした品は必ず外して処理するか、葬儀社と相談して取り扱いを決めるべきです
その他の注意が必要な副葬品
革製品や合成繊維製品、クッション材などの素材は燃焼時に有害ガスを出す可能性があり、厚い書類や大型の布団なども火葬時間や遺骨の状態に影響します
これらは焼却に適したものかどうかを判断し、火葬場の指示に従うことが望まれます
棺に入れるべき供養品とは
故人を偲ぶ気持ちを表すために何かを納めたい場合は、燃焼時に問題を生じさせない素材を選ぶことが大切です
紙にしたためた手紙や写真、生花(少量)、自然素材の布や小さな思い出の品などは比較的安全であり、葬儀社もそうした「焼却可能で環境負荷が低い」副葬品を推奨しています
事前に葬儀社と相談することで、故人らしい送り方を保ちつつ安全性も担保できます
故人の思い出の品を選ぶポイント
故人が普段愛用していた軽い布製のハンカチや、紙に書いた手紙、写真など、燃焼して有害物質を出さないものを優先するのが基本です
思いを伝える手段は多様であり、焼却に適さない品は別途保管や供養方法(骨壺の周りに飾る、供養棚に置くなど)を検討するとよいでしょう
焼却可能で安全な副葬品の例
焼却に適した副葬品としては紙の手紙や写真、自然素材の小物、少量の生花などが挙げられます
これらは環境負荷が低く、火葬場の運用に大きな影響を与えにくいため多くの施設で許容されています
ただし、数量や素材については施設ごとのルールに従ってください
葬儀社が推奨する供養の方法
葬儀社は安全面と遺族の気持ちを両立させる提案を持っています
たとえば、燃えない大切な品は一旦遺族が保管して後で納骨の際に改めて供えるか、写真や手紙を棺に入れる代わりに告別式で読み上げるなど、柔軟な代替案を提示することが多いです
事前相談をすることで不安を減らし、故人らしい送り方を実現できます
棺にまつわる正しい知識を持つ重要性
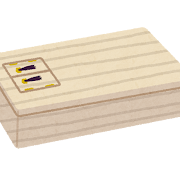
伝統や地域習慣を尊重する一方で、現代の火葬設備や環境規制に配慮することは欠かせません
誤った風習を無批判に続けると、火葬場の稼働や環境に悪影響を与え、最終的には地域全体の葬送サービスの質やコストに跳ね返る可能性があります
自治体や斎場が出す注意喚起に耳を傾け、故人を大切に送りつつ安全も確保する姿勢が求められます
誤った風習を避けるためにできること
まずは葬儀を依頼する葬儀社や火葬場に、副葬品のルールを確認してください
地域によって許容されるものと禁止されるものが異なるため、事前確認がトラブル防止につながります
必要であれば代替の供養方法を相談し、家族の気持ちに沿った形を一緒に作ることが大切です
遺族が安心して供養するための工夫
大切なのは形式そのものではなく、故人への思いです
燃やせない遺品は写真や手紙で代替したり、遺骨安置後に別途手厚く弔うなど方法は複数あります
葬儀社と話し合い、意味のある行為を選ぶことで遺族も安心できます
今後の葬儀文化と棺のあり方
高齢化や火葬件数の増加に伴い、火葬場の運用負荷や環境配慮はこれまで以上に重要になります
伝統を尊重しつつも、新しい時代に合った供養の在り方を地域で模索することが求められます
自治体の周知や葬儀業界のガイドライン整備を通じて、故人・遺族・地域社会の三者が納得できる形を作っていくことが今後の課題です
まとめ
以上が、札幌市の注意喚起を踏まえた「棺に10円玉を入れる」習慣の背景と現代的なリスク、そして安全な供養の提案です
具体的に「自分の場合どうするか」を決める際は、葬儀社や火葬場へ事前に相談することを強くおすすめします

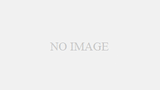
コメント